個人事業主であっても、多くの場合には社会保険への加入手続きが必要になります。しかし「うちは小規模だから」「個人事業でお手伝いのような感じだから」と、きちんと手続きをせず、結果的に大きなトラブルになるケースが少なくありません。
本記事では、個人事業主が従業員を雇った場合に、どのような社会保険の手続きが必要になるのかを詳しく解説します。これから従業員を雇おうと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 個人事業主でも、従業員を1人でも雇ったら、労災保険や雇用保険、健康保険、年金保険といった社会保険に加入する必要があるよ!
- 手続きは、健康保険・年金保険の手続きと、労災保険・雇用保険の手続きが必要になるので、それぞれ早めに準備しておこう。
- 社会保険とは別に、税金の手続きも必要になるので、忘れずに行おう!
目次
個人事業主でも従業員を雇ったら社会保険加入が必要
個人事業主が従業員を雇った場合であっても、その従業員は社会保険に加入しなければなりません。
まず、ほとんどの場合に加入義務が生じるのが「労働保険」と呼ばれる、労災保険と雇用保険です。
また、狭義の社会保険と呼ばれる、健康保険・年金保険・介護保険についても、加入義務が生じる場合があります。
法人じゃないから大丈夫、小規模だから大丈夫と思わず、原則として何らかの保険の加入手続きが必要と考えて、しっかりと準備していきましょう。
個人事業主が従業員を雇った場合に必要な手続き
個人事業主が従業員を雇った場合、以下の手続きが必要になります。
- 社会保険関係
- 源泉徴収関連
- 給与支払い関係
- 労働条件通知の作成・交付
なお、人数によって必要な手続きは異なるので、注意しましょう。人数ごとの必要な手続きについては、後半の項目で解説します。
社会保険関係
社会保険関連とは、いわゆる年金保険や健康保険などの手続きです。個人事業主の場合は、法人とは異なり、従業員が常時5人未満だった場合は加入義務はありません。
社会保険の具体的な種類や、手続きの内容については、本項目以降で詳しく解説していきます。
労働保険関係
社会保険とは別に、労働保険と呼ばれるものもあります。
- 労災保険:労働中の災害によるケガ・病気等に対して給付等を実施
- 雇用保険:失業や就業困難などの場合に、生活維持・再雇用促進等のための休符等実施
参考:厚生労働省『労働保険とは』
社会保険とは異なり、労働保険は従業員を1人でも雇ったら、従業員は強制加入となります。手続きについては、この後の項目で詳しく解説します。
労働条件通知書の作成・交付
労働条件通知書とは、名称のとおり、労働条件について記載し、従業員に対して通知するための書類です。労働基準法第15条、および労働基準法施行規則第5条で交付が義務付けられている書類なので、必ず作成・交付しましょう。
どういった業務内容か、契約期間はいつからいつまでか、給与はいくらか、といった情報を記載しましょう。具体的には、以下のような内容を記載します。
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
※2は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。
※7〜14は、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、明示する必要はありません。
労働条件通知書とは別に「雇用契約書」というものもあります。こちらは交付義務はないものの、昨今は「労働条件通知書 兼 雇用契約書」というかたちで作成するケースが多いでしょう。
雇用契約書について、法的に定められた記載内容はありません。労働条件通知書に追加して、必要な情報を適宜記載しておきましょう。
源泉徴収関連
源泉徴収とは、所得からあらかじめ所得税分を差し引いておくことです。よく「額面給与と手取り給与」という言い方をしますが、額面給与から源泉徴収や保険料を差し引くため、手取り給与は少なくなるのです。
源泉徴収額は、年度や給与額、扶養人数などによって異なります。今回は2024年分の、社会保険料等を差し引いた後の所得金額と扶養人数ごとの源泉徴収額を紹介します。
| 月額給与/扶養者 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 99,000円以上101,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 149,000円以上151,000円未満 | 2,980円 | 1,360円 | 0円 |
| 199,000円以上201,000円未満 | 4,770円 | 3,140円 | 1,530円 |
| 209,000円以上211,000円未満 | 5,130円 | 3,500円 | 1,890円 |
| 248,000円以上251,000円未満 | 6,530円 | 4,920円 | 3,300円 |
| 299,000円以上302,000円以上 | 8,420円 | 6,740円 | 5,130円 |
| 308,000円以上311,000円以上 | 9,160円 | 7,110円 | 5,490円 |
| 317,000円以上320,000円未満 | 9,890円 | 7,470円 | 5,860円 |
| 329,000円以上332,000円未満 | 10,870円 | 7,960円 | 6,350円 |
| 338,000円以上341,000円未満 | 11,610円 | 8,370円 | 6,720円 |
| 347,000円以上350,000円未満 | 12,340円 | 9,110円 | 7,090円 |
源泉徴収税の手続きとしては、まず従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
本記事をご覧の方の中にも、アルバイト雇用や正社員雇用された際に、右上に〇で囲んだ扶のマークのある書類を渡された覚えのある方がいるのではないでしょうか。それが、まさに給与所得者の扶養控除等申告書です。
そして、申告してもらった扶養人数等に応じて源泉徴収税を確認し、給与支払い時に差し引きます。差し引いた源泉徴収税は、原則として徴収日翌月10日までに納付しましょう。
なお、従業員10人未満の場合は、年2回まとめて納付できる特例もあります。
社会保険にはどんなものがある?加入条件も紹介
社会保険はさまざまな保険を一括りでいう呼び方です。一般的に、社会保険というと以下の保険を指します。
- 健康保険
- 年金保険
- 介護保険
- 労災保険
- 雇用保険
それでは、各保険について詳しく解説します。
健康保険
健康保険とは、病気や怪我をした際の診察料や薬代を一部負担してもらえるものです。日本は国民皆保険制度を導入しているので、どんな人でも加入対象となっています。
- 国民健康保険:個人事業主など
- 被用者保険:会社員や公務員など
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の後期高齢者など
一定の条件を満たす個人事業所は「適用事業所」となり、従業員を被用者保険に加入させ、保険料を折半で支払う必要があります。
- 組合管掌健康保険(健保組合):大企業従業員など
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業従業員など
- 共済組合:公務員や私立校教職員など
- 船員保険:船員
個人事業主が雇っている従業員については、協会けんぽに加入するケースがほとんどでしょう。
適用事業者の条件
個人事業の場合、以下の条件を満たす場合には「適用事業所」という扱いになり、従業員を健康保険や年金保険に加入させる義務が生じます。
- 法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
- 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
引用:日本年金機構『事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき』
なお、2022年(令和4年)からは、以下の士業を営む事業所についても、常時5人以上の従業員がいる場合には、保険の強制加入対象となります。
- 弁護士
- 沖縄弁護士
- 外国法事務弁護士
- 公認会計士
- 公証人
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 海事代理士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
引用:日本年金機構『健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)』
なお、適用事業所の条件を満たしていない場合でも、以下の条件を満たせば適用事業所になることが可能です。
- 従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意する
- 事業主の申請に対して厚生労働大臣の認可を得る
参考:日本年金機構『適用事業所と被保険者』
加入対象となる従業員
適用事業所となった場合でも、従業員全員が加入対象になる訳ではありません。従業員の就労状況によって、保険加入が可能かどうかは異なります。
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 2ヵ月を超えて働く予定がある
- 学生でない
参考:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト『社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について』
上記の条件を満たす場合、その従業員は健康保険をふくむ社会保険の加入対象者となります。
年金保険
年金保険は、現役時に一定金額を納めていき、老後に給付を受け取れる保険です。
年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。
- 国民年金:全国民
- 厚生年金:会社員や公務員など企業等に雇用されている人
- その他:企業年金や確定拠出年金など任意加入のもの
年金保険の適用事業所となる条件や、従業員側の加入条件については、健康保険と同様です。
介護保険
介護保険は、40歳以上の人が加入する保険です。要介護・要支援認定を受けて介護サービスを利用することになった場合に、自己負担分が1〜2割で済むようになります。
原則として40歳以上のすべての人が加入対象ですが、以下の方は対象になりません。
- 海外住居者(国内に住所がない人)
- 短期滞在の外国人(3ヵ月以下)
- 身体障害者養護施設等に入所している人
参考:日本製鉄健康保険組合『介護保険制度』
保険料は自治体や所得によって異なります。平均納付額は約6,000円となっていますが、あくまで平均額なので、正確な金額は各自治体のホームページをご確認ください。
参考:厚生労働省『令和5年度 介護納付金の算定について(報告)』
労災保険
労災保険は、労働災害によるケガや病気の治療費や薬代、休業時給与などに関する給付を受けられる保険です。
従業員が1人でもいる場合、雇用形態(アルバイト・パート・正社員・派遣など)に関わらず、必ず加入する必要があります。これを「当然適用事業」といい、健康保険や年金保険と比べて適用事業者の範囲が広いのが特徴です。
なお、以下の事業者に関しては強制適用となる適用事業者ではなく、任意適用となる「暫定任意適用事業」という扱いになります。暫定任意適用事業の場合、労働者の過半数が賛成し、承認を得た場合のみ、適用事業として申請できます。
- 労働者数5人未満の個人経営の農業であって、特定の危険又は有害な作業を主として行う事業以外のもの
- 労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業
- 労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業
引用:厚生労働省 群馬労働局『労働保険関係の成立と対象者』
労災保険料は業種や賃金によって異なります。最新の保険料率に関しては厚生労働省のページをご確認ください。保険料は、健康保険や年金保険とは異なり、全額事業主負担となります。
なお、上記のような業種や、事業主のように強制適用ではない事業者についても「特別加入」という方法で労災保険に加入できる場合があります。以下の記事では、フリーランスの労災保険加入について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
雇用保険
雇用保険は、失業した際の生活費や、再就職のための給付を受けられる保険です。従業員を1人でも雇っていれば、適用事業者となります。
ただし、労災保険と同様に、特定の条件を満たす農水林業に関しては「暫定任意適用事業」という扱いとなるので注意しましょう。暫定任意適用事業の場合、労働者の1/2以上の同意を得て、申請が承認された場合に適用事業者となります。
雇用保険は、被保険者になるための条件が設けられています。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合。- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 (※)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
引用:厚生労働省『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』
上記の条件を満たす場合は、雇用保険の対象となり、失業した場合には失業給付、再就職した際には再就職手当が受け取れます。
雇用保険の保険料は、交通費をふくむ給与額に雇用保険料率をかけて算出します。保険料率は年度や業種によって異なりますが、2025年度の一般事業の保険料率は14.5/1,000です。
雇用保険に関しては、全額事業主負担ではなく、また折半でもなく、労働者負担分と事業主負担分の保険料率がそれぞれ決められています。
例えば前述した一般事業保険料率14.5/1,000のうち、労働者負担は5.5/1,000、事業主負担は9.0/1,000です。
最新の保険料率については、厚生労働省のページをご確認ください。
【1人・2人・5人】ケースごとの社会保険の加入手続き
ここまで解説してきたように、社会保険のなかにも「従業員1人でも雇用すれば強制適用」というものもあれば、人数に応じて強制適用だったり、そうでなかったりする保険もあります。
それでは、従業員1〜2人の場合と、5人以上の場合とで、加入手続きが必要となる保険を確認していきましょう。
従業員1人・2人
従業員1〜2人の場合、健康保険や年金保険の適用事業からは基本的に外れます。そのため、労働保険と呼ばれる「労災保険」と「雇用保険」の新規適用事業としての手続き、および従業員の保険加入手続きをすれば良いでしょう。
ただし、健康保険や年金保険の任意適用事業として保険加入をしたい場合は、加入手続きが必要となります。また、労働保険については業種によっては適用事業ではなくなる点や、就労状況によって被保険者の対象外となる点に注意しましょう。
従業員5人以上
従業員が5人以上になると、社会保険の加入義務が生じます。そのため、労災保険・雇用保険の手続きとは別に、健康保険・年金保険(厚生年金)の加入手続きが必要です。
なお、健康保険や年金保険の保険料は、事業主と労働者で折半となります。保険料を滞りなく納められるように、保険料をあらかじめ計算しておき、どれくらいの負担が生じるか把握しておきましょう。
社会保険・労働保険の種類ごとの加入手続き
「自分がどの保険の加入手続きをする必要があるのか」が把握できたら、さっそく手続きを進めていきましょう。以下では、保険の種類ごとに加入手続きの方法を解説します。
健康保険
健康保険にはさまざまな種類がありますが、今回は「協会けんぽに、事業所として初めて加入する」というケースを想定して解説します。
まず、適用事業者になるため「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出します。提出期限は事実発生日から5日以内で、所轄の年金事務所窓口で提出するか、郵送、また電子申請もできます。
届出書を提出する際、強制適用となる個人事業主の場合は、事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)が必要です。
また、被保険者の「被保険者資格取得届」を、被保険者に扶養家族がいれば「被扶養者(異動)届」を併せて提出しましょう。
なお、任意適用の場合は新規適用届ではなく「任意適用申請書」に記入・提出します。
また、保険料を口座振替で納付する場合は「健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書」も提出してください。こちらの申出書は、事前に金融機関での手続きが必要になるので、余裕をもって準備しましょう。
参考:日本年金機構『1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき』
年金保険
年金保険(厚生年金)に加入する場合、手続きは健康保険と一緒に行えます。別々に手続きをする必要はありません。
前述のとおり「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出しましょう。また、事業主の世帯全員の住民票・被保険者資格取得届・被扶養者届など、前述した書類も併せて提出します。
介護保険
介護保険は、被保険者の方がいれば、市区町村もしくは健康保険組合が自動的に手続きをしてくれるので、事業所側での手続きは扶養です。
健康保険料とあわせて、介護保険料が徴収されるようになりますので、加入対象となる年齢の従業員がいる場合には、保険料納付が確実に行えるよう注意しましょう。
労災保険
労災保険の手続きは、一元適用事業か二元適用事業かで、手続きの方法が異なります。一元適用事業は、労災保険と雇用保険の手続きをまとめて行える事業、二元適用事業は別々に行う事業です。以下の二元適用事業以外は、自動的に一元適用事業となります。
- 都道府県及び市区町村が行う事業
- 1に準ずるものの事業
- 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
- 農林・水産の事業
- 建設の事業
引用:厚生労働省『労働保険の基礎知識』
一元適用事業の場合、以下の流れで手続きを行います。
- 保険関係成立届を労働基準監督署に提出
- 概算保険料申告書を労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行いずれかに提出
- 雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出
- 雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出
※提出先はそれぞれ所轄の機関
参考:厚生労働省『労働保険の成立手続』
各書類の提出期限は、以下のとおりです。
- 保険関係成立届:保険関係成立日の翌日から起算して10日以内
- 概算保険料申告書:保険関係成立日の翌日から起算して50日以内
- 雇用保険適用事業所設置届:設置日翌日から起算して10日以内
- 雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで
参考:厚生労働省『労働保険の成立手続』
二元適用事業の場合は、上記のような書類を、労災保険と雇用保険それぞれ別に提出していきます。詳しくは、厚生労働省のページをご確認ください。
雇用保険
雇用保険の手続きの流れは、労災保険と同じです。一元適用事業の場合は2つの保険の手続きをまとめて行うので、別途何か手続きをする必要はありません。
従業員を雇った場合の税金について
従業員を雇った場合、給与から「源泉徴収」をしなければなりません。では、源泉徴収とはなにか、税金の手続きはどのようにするのか、以下で詳しく解説します。
源泉徴収税について
源泉徴収は、所得税分をあらかじめ給与から天引きしておく制度のことです。概算で金額を決め、天引きし、もし源泉徴収しすぎていたら年末調整をしたうえで還付されます。
年末調整の流れ
年末調整をする際は、まず従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。給与に関して、配偶者控除や障害者控除などを受ける際に必要な書類です。
また、確定拠出年金の掛金があったり、配偶者控除を受ける場合には「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書(※)」「各種控除証明書類」「住宅借入金等特別控除申告書」を提出してもらいましょう。
もし転職で中途入社した人がいれば「前職での源泉徴収票」を提出してもらってください。
そして、上記書類を参照し、課税給与所得金額を計算し、年長所得税額・年超年税額を算出、申告します。
年末調整関連の書類は、所轄税務署に提出、もしくはe-Taxで電子申請が可能です。
※「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
個人事業主のためのLINE!
- 計36Pの税金・節税丸わかり資料GET!
- 税金・節税・助成金・法律…逃しがち情報を週1でGET!
- →事業成長をGET!
\登録者2万人超!/

個人事業主のためのLINE
- 36Pの税金/節税対策資料GET!
- オトク情報を週1でGET!
- →事業成長をGET!
\登録者2万人超!/
個人事業主が従業員を雇った場合のよくある質問
個人事業主が従業員を雇った場合、以下のような疑問を抱く人が多くいるでしょう。
- パートを雇った場合の社会保険や税金は?
- 社会保険に加入しなかった場合はどうなる?
- 専従者の国民年金は免除にできる?
- 従業員の給与や社会保険料は経費にできる?
それでは、よくある4つの質問に回答していきます。
パートを雇った場合の社会保険や税金は?
パートを雇った場合でも、業種や就労状況に応じて各種社会保険に加入する必要があります。特に労働保険は、雇用形態に関わらず強制加入となるケースがほとんどなので、注意しましょう。
源泉徴収に関しても、通常どおり行う必要があります。源泉徴収をしたら、年末調整もあわせて行う必要がありますが、個人事業主側で年末調整する場合と、労働者が個人で確定申告するケースとがあるので、状況に応じて判断しましょう。
社会保険に加入しなかった場合はどうなる?
社会保険に加入する義務があるのに加入しなかった場合、以下のような罰則があります。
- 6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金(健康保険法第208条)
- 過去2年間に遡及して保険料を徴収
- 従業員負担分の保険料も企業が負担
- 延滞金が発生
- 公共職業安定所(ハローワーク)への求人掲載不可
参考:e-Gov『健康保険法』
また、従業員やその家族から、損害賠償請求をされる可能性もあります。このように、加入義務があるのに未加入な状態を放置してしまうと、さまざまなリスクがあるため、必ず加入するようにしましょう。
専従者の国民年金は免除にできる?
専従者の国民年金保険料は、原則として免除にすることはできません。
ただし、以下の基準を満たす場合は、免除や猶予の申請ができます。
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 納付猶予制度:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
参考:日本年金機構『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度』
また、2026年から施行される免除措置により、国民年金第一号被保険者が出産した場合、子どもが1歳になるまでは保険料支払いが免除となります。
年金保険料の支払いが難しい場合には、各種制度の活用を検討しましょう。
従業員の給与や社会保険料は経費にできる?
従業員の給与や社会保険料は、人件費として経費計上できます。健康保険料や年金保険料などの労使折半での事業主負担分については「福利厚生費」や「法定福利費」として計上することが可能です。
まとめ
個人事業主であっても、従業員を1人でも雇ったら、社会保険の加入義務が生じる可能性があります。加入義務があるのに未加入な状態が続いていると、さまざまな罰則が課される可能性があるので、必ず手続きをしましょう。
また、社会保険の種類によっては、保険料を一定額もしくは全額、事業主が負担する必要があります。まず、自分の従業員は加入義務があるのか、また加入する場合には保険料がいくらで、事業主負担はいくらなのかを把握し、遅延なく支払えるように資金繰りしていきましょう。

- 個人事業主でも、従業員を1人でも雇ったら、労災保険や雇用保険、健康保険、年金保険といった社会保険に加入する必要があるよ!
- 手続きは、健康保険・年金保険の手続きと、労災保険・雇用保険の手続きが必要になるので、それぞれ早めに準備しておこう。
- 社会保険とは別に、税金の手続きも必要になるので、忘れずに行おう!

.png)

-485x306.png)
-485x306.png)
-485x306.png)
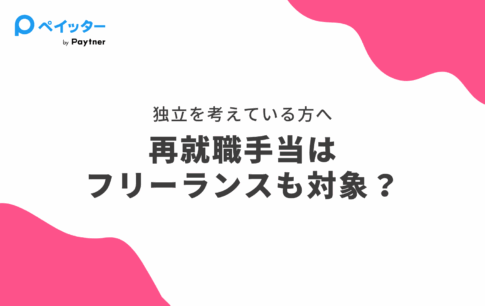
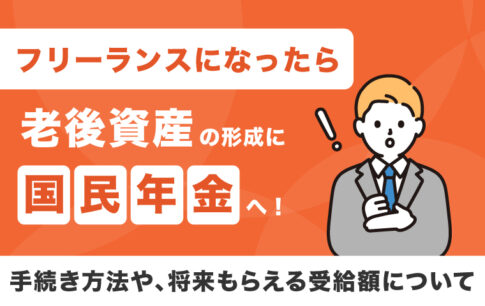


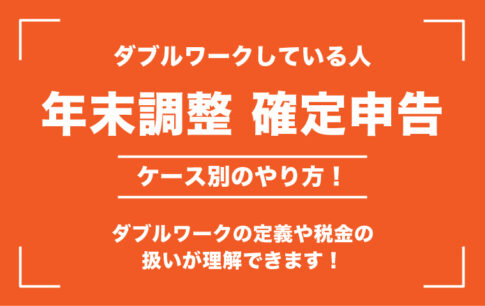
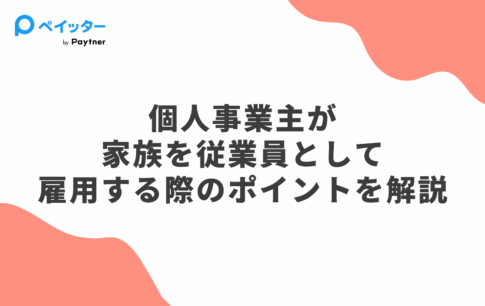

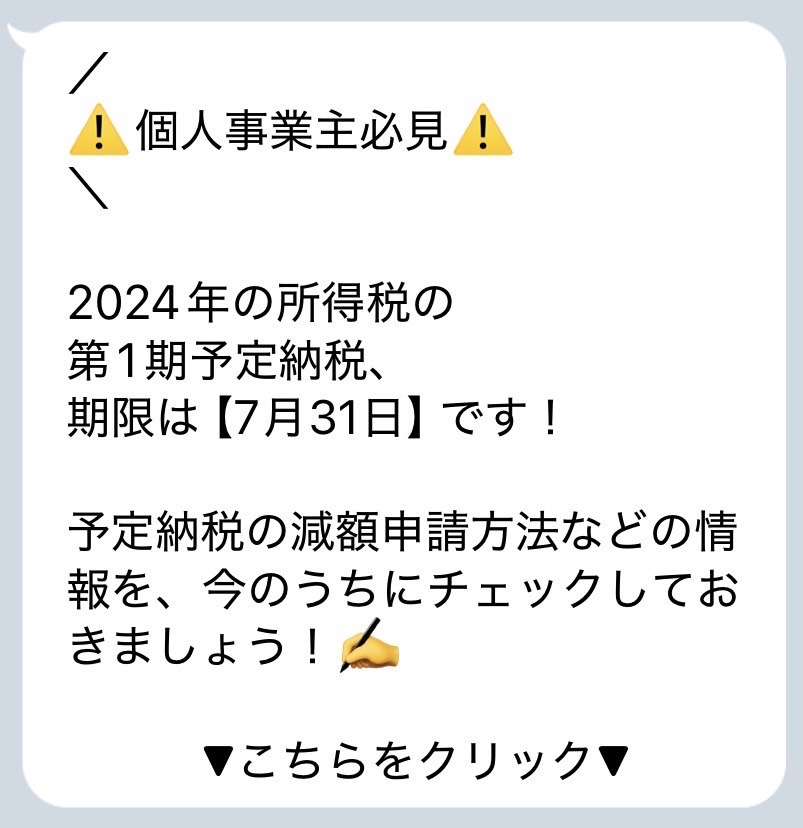
-485x306.png)

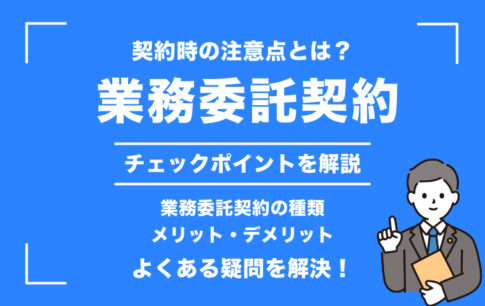
-485x306.png)
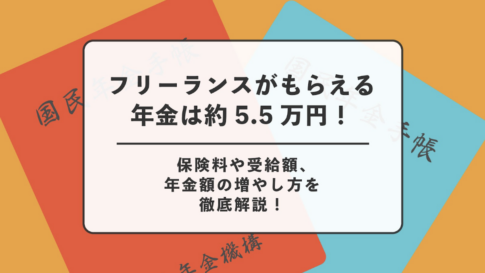
-485x306.png)
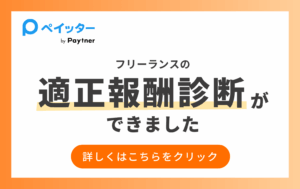
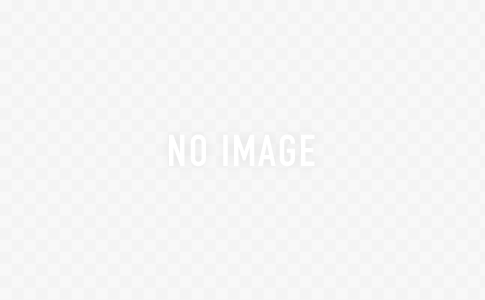
-485x306.png)
-485x306.png)
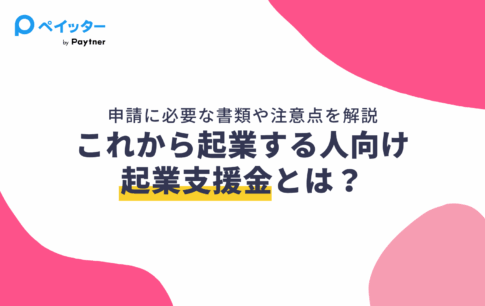

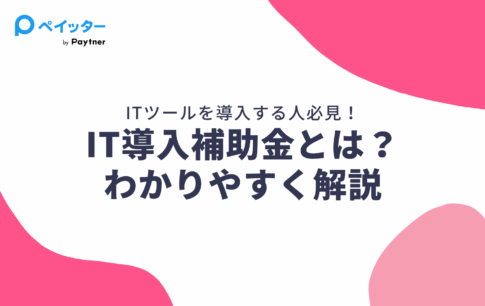
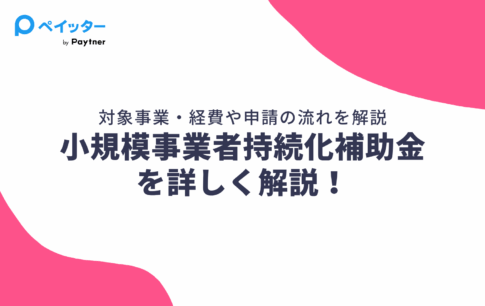
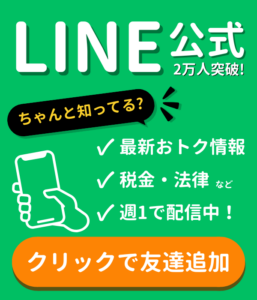
\ お金の不安、LINEで減らそう! /
フリーランスのための
「知って得する情報」を毎週配信中!
✅ 節税&経費のコツ
✅ 補助金・助成金の申請ガイド
✅ 最新の法律情報
\ LINE登録2.5万人突破! /