少子高齢化によって、後継者不足による廃業が増加しています。また、突然事業主が亡くなり、事業承継をどうするか悩むケースも少なくありません。
大切な事業と顧客を守るために、事業承継について早めに考えておくのが大切です。
本記事では、個人事業は事業承継できるのかを解説します。
目次
個人事業の事業承継は可能!法人とは異なるポイント
個人事業を後継者に承継するのは可能です。ただし、個人事業主は法人と異なり、代表取締役という役職がなく、事業主のポジションを譲り渡すということはできません。新事業主が新たに開業をして、事業を受け継ぐという流れになります。事業承継時にかかる税金や手続きの流れ、利用できる制度や補助金についても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 個人事業の事業承継は可能だよ!
- 承継方法は贈与・相続・売却があるよ
- 補助金や税負担軽減制度の活用も検討しよう!
個人事業の承継の現状
中小企業庁が公開している「中小企業白書」では、事業承継に関する統計データが掲載されています。ではまず、事業主と承継者との関係についてデータを見てみましょう。
- 配偶者:3.1%
- 子ども(男性):75.3%
- 子ども(女性):1.4%
- 子どもの配偶者:3.4%
- 兄弟姉妹:1.4%
- その他の親族:2.0%
- 親族以外の役員・従業員:4.4%
- 社外の第三者:6.8%
- その他:2.4%
引用:中小企業庁『中小企業白書2019 第2部』
上記データを見ると、後継者の大半は子ども(男性)が占めていることがわかります。次に、後継者決定から承継までにかかった期間を見てみましょう。
- 1年未満:61.3%
- 1年以上3年未満:21.9%
- 3年以上5年未満:6.5%
- 5年以上:10.3%
引用:中小企業庁『中小企業白書2019 第2部』
多くの事業主が、1年未満で事業承継をしているようです。同調査では、89.4%の事業主が事業の全てを引き継いでおり、86.4%の事業主が事業用資産の全て、または一部を引き継いでいます。つまり、多くの事業主は非常に短期間で事業のほとんどを後継者に承継している、といえるでしょう。
個人事業の事業承継3つの種類
個人事業を承継する方法として、以下3つがあります。
- 贈与
- 相続
- 売却(M&A)
それぞれのケースについて、どのような内容か、どんな人が承継するときにその方法を採るのかを解説します。
贈与
贈与は、事業主が生きている間に事業を承継する方法です。贈与の場合、家族・親族・社内外の人など、贈与先を任意で選びやすいのがメリットでしょう。また、どのタイミングでどのように贈与するか調整できるのも、贈与のメリットです。
ただし、一度に事業用資産を贈与する場合、相続税よりも高額な贈与税が発生する可能性が高いので注意しましょう。
相続
相続は、事業主が亡くなった後に承継するケースです。被相続人は、原則として親や配偶者といった「法定相続人」に限定されており、相続する優先順位(相続順位)も決まっています。
しかし、遺言を残しておけば、相続順位はある程度無視できますし、第三者に相続することも可能です。ある程度の制約はあるものの、相続の方法や範囲を柔軟に指定することができます。例えば、事業の後継者として適任な人物が親族以外にいる場合、遺言によってその人物に事業を引き継がせることが可能です。また、遺言を公正証書として残しておけば、相続争いのリスクを軽減することができます。
売却(M&A)
事業用資産やブランドなどを売却する方法もあります。事業承継によって利益を得たいとき、後継者不在のとき、事業に精通した第三者に承継したいときに適した方法です。事業を譲り渡して、対価を受け取るので、承継よりも譲渡のイメージが強いでしょう。
事業売却は魅力的な方法ですが、取引先への説明が必要な点や、売却によって取引が打ち切りになるリスクがある点には注意が必要です。また、買い手は負債を引き取らなくて良いので、売り手側に負債が残ってしまうケースもあります。
*贈与と相続の違いは?
贈与と相続の違いは、事業主が存命か、亡くなった後かです。多くの場合、生きている間に受け継ぐ場合には贈与、亡くなってから事業承継する場合は相続となります。
贈与と相続では、手続きや税金が異なります。基本的には贈与税のほうが高額ですが、贈与の場合は何回かに分けて贈与できるので、トータルでの税額を減らすことが可能です。ただし、贈与から3年以内に亡くなった場合は、相続財産という扱いになります。
また、相続財産のすべてを身内の一人に相続させたり、第三者に相続させたりすると、誰かの住居がなくなってしまったり、生活が困難になったりする可能性があります。
そのため、法定相続人に対しては最低限の遺産(遺留分)を相続する権利が認められています。
個人事業を事業承継する際の流れ
個人事業を承継する場合、以下のような流れで手続きを進めます。
- 現事業主が廃業届を提出
- 新事業主が開業届を提出
- 事業に関する許認可の手続き
- 取引先や従業員に対する引継ぎ
それでは、事業承継の流れを以下で詳しく解説します。
現事業主が廃業届を提出
まず、現在の事業主が「個人事業の開業届出・廃業届出等手続(廃業届)」を、所轄の税務署に提出します。提出は、廃業の事実があった日から1か月以内です。
提出方法は、窓口へ持参・郵送・e-Tax(電子申請)から選択できます。
【あわせて提出】確定申告・消費税・予定納税関連の書類
廃業届を提出するタイミングで、必要であれば所得税や消費税などに関する書類も提出しましょう。
- 青色申告していた方:所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 消費税の課税事業者:事業廃止届出書
- 予定納税があった方:所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
- 従業員を雇っていた方:給与支払事務所等の廃止届出書
該当する方は、上記の書類もあわせて提出してください。
新事業主が開業届を提出
廃業に関する手続きが完了したら、新しい事業主が「個人事業の開業届出・廃業届出等手続(開業届)」を提出します。書式は、廃業届と開業届どちらも同じです。「届出の区分」で「開業」を選択してください。
【あわせて提出】確定申告・専従者給与・消費税関連の書類
青色申告をしたい、従業員を雇いたいといった場合には、以下の書類もあわせて提出しましょう。
開業届とあわせて提出する書類
- 青色申告をする方:所得税の青色申告承認申請書
- 従業員を雇う方:青色事業専従者給与に関する届出、与支払事務所等の開設届出書
- インボイス登録する方:適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)
なお、インボイス登録をする場合、申請のタイミングや相続方法などによって、申請書の書き方が異なります。詳しくは、国税庁のフローチャートをご覧ください。
事業に関する許認可の手続き
建設業・飲食業などの許認可が必要な事業を承継する場合、現在の許認可を引き継ぐことはできません。新事業主は新たに許認可を取得する必要があります。
なお、建設業や飲食業などの許認可は、取得までに時間がかかるものが多くあります。まずどんな許認可が必要なのか、それぞれどのように手続きするのか、取得までにおおよそどれくらいの時間がかかるかを調べておきましょう。
取引先や従業員に対する引継ぎ
事業承継をする場合は、取引先や従業員に対する引継ぎも重要です。
取引先に対しては、新しい事業主がどんな人物なのか、どのように引き継ぐのか、今後も同様のサービスを提供できるかなどをしっかりと説明しましょう。
また従業員に対しては、今後も同じように働けるのか、給与体系は変わらないのかなど、不安に思っていることをヒアリングしつつ、丁寧に説明しましょう。元事業主は、新しい事業主と従業員とが円滑にコミュニケーションを取れるようサポートするのも大切です。
LINEであなたに合った補助金を診断!
【今すぐ】あなたの事業種別・業歴・業種に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/

LINEで補助金診断!
【今すぐ】あなたの事業に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/
青色事業なら「個人版事業承継税制」が使える!
青色申告をしている青色事業の場合、個人版事業承継税制を活用して、納税の猶予を受けることができます。それでは、同制度について以下で詳しく解説します。
個人版事業承継税制とは?
個人版事業承継税制とは、事業承継によって受け継がれた資産について、相続税・贈与税の納付を猶予、もしくは免除してもらえる制度です。法人のみを対象としていましたが、2019年度からは個人事業も対象となっています。
日本は贈与税・相続税の負担が大きいことでも知られており、この税負担が事業承継を難しくしている要因ともなっています。特に、土地や不動産は評価額によって大きく変わってしまうので、想定よりも税負担が重く、相続が難しくなるケースも少なくありません。
こうした廃業を減らし、有益な事業を少しでも多く後世に残すべく、事業承継税制がつくられました。
制度利用の条件
前提として、本制度は青色事業でないと利用できません。白色申告をしていた場合は対象外となります。
また承継期間にも条件があり、2019年1月1日〜2028年12月31日までに、事業用資産を承継した場合が対象です。
対象となる資産
対象となる承継資産は「土地(借地権)」「建物」「減価償却資産」のうち、贈与・相続する前年分の確定申告の貸借対照表に計上されていたものを指します。なお、それぞれ以下のような制限もあります。
- 土地(借地権):事業用で400㎡以下の部分
- 建物:床面積800㎡以下の部分のみ、不動産用物件は対象外
- 減価償却資産:工場設備や電子機器、車両、乳牛など
事業と事業者・後継者の条件
制度の対象となる事業は、資産管理事業・性風俗関連特殊営業に該当していない事業です。
また、先代事業者は、前述のとおり青色申告をしている場合が対象となります。贈与の場合は、生前の制度利用手続きが必須で、廃業届の提出が必要となります。
後継者に関しては、開業届と青色申告承認申請書の提出や、計画書の提出、経営承継円滑化法の認定取得が求められています。また、18歳以上で、贈与日までに3年以上、同事業もしくは同種事業に従事していることも条件です。
詳しい条件については、以下のパンフレット(国税庁)をご覧ください。
参考:国税庁『個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし』
手続きの流れ
個人版事業承継税制は、以下の流れで手続きを進めます。なお、贈与と相続で流れや提出書類が異なりますので、ご注意ください。
- 個人事業承継計画を策定
- 税理士・商工会・商工会議所等の認定経営革新等支援機関から所見をもらう
- 都道府県知事に提出(提出先は各都道府県の担当窓口*)
- 贈与・相続
- 都道府県知事から「円滑化法の認定」を受ける
- 開業届等を提出後、本制度関連の書類を所轄税務署に提出、一定の担保を提供
- 猶予期間中、事業を継続、必要に応じて四類を提出
- (贈与)先代事業者の死後、免除届出書・申請書等を提出
- (相続)後継者の死亡等があった場合は、免除届出書・申請書等を提出
個人事業の事業承継でかかる税金
個人事業を承継する場合、以下の税金がかかります。
- 贈与税(生前贈与の場合)
- 相続税(相続の場合)
- 所得税(事業売却の場合)
それでは、各税金について詳しく解説します。
贈与税(生前贈与の場合)
先代事業主が生きている間に、事業用資産を承継した場合にかかる税金です。贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、どちらかを選べます。
暦年課税
暦年課税は、1月1日〜12月31日の1年間で贈与された財産の価額合計から、基礎控除額110万円を差し引いた分に課税する方式です。価額合計が110万円以下であれば贈与税は非課税となり、申告も不要です。
それでは、特例贈与財産に関する税率を紹介します。なお、夫婦間・兄弟間での贈与や、未成年の子どもへの贈与は「一般贈与財産」となり、税率が異なるのでご注意ください。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 415万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 640万円 |
例えば贈与財産の価額が800万円だった場合、「(800万円 – 110万円) × 40% – 190万円 = 86万円」が贈与税の納税額となります。
相続時精算課税
相続時精算課税は、対象者が相続した場合に選択できる制度です。本制度を選択する場合は「相続時精算課税選択届出書」を提出しましょう。なお、選択後に暦年課税への変更はできなくなります。
- 対象となる贈与者:贈与者は贈与実施年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母
- 対象となる受贈者:贈与実施年の1月1日に18歳以上で贈与者の直系卑属である推定相続人、または孫
※対象者には例外もあります。詳しくは国税庁HPをご覧ください。
相続時精算課税の場合、贈与財産価額から基礎控除:110万円、特別控除:限度2,500万円を差し引いた金額に、一律20%をかけて税額を出します。
参考:国税庁『No.4103 相続時精算課税の選択』
相続税(相続の場合)
相続税は、亡くなった親・配偶者などから財産を相続した場合にかかる税金です。財産や土地など多くの相続財産が課税対象ですが、生命保険金・死亡退職金・墓地・墓石・神具などは非課税となっています。
相続税の基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で決定されます。例えば、法定相続人が2人なら、基礎控除は4,200万円で、価額合計が4,200万円以下なら非課税、申告不要となります。
相続税は以下の方法で計算します。
- 相続した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を合わせる
- 1から非課税財産と債務・葬式費用を差し引き「純資産価額」を算出
- 純資産価額に、相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、課税価額を算出
- 3から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出
- 法定相続分で按分し、超過累進税率を適用し、相続税の総額を算出
- 実際の相続割合で按分する
- それぞれに税額控除を適用する
参考:政府広報オンライン『相続税はいくらから?基礎控除とは?相続税の基本を確認!』
相続税の超過累進税率は、以下のとおりです。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
所得税(事業売却の場合)
事業を売却した場合、売却益に対して所得税がかかります。所得税額は、以下のように計算します。
- 売上 – 必要経費 – 所得控除 = 課税所得
- (課税所得 × 税率) – 税額控除 = 所得税額
税率は、以下のようになっています。
■平成27年分以降の所得税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
LINE限定の最新お役立ち情報配信中!
【実際のLINEトーク画面】
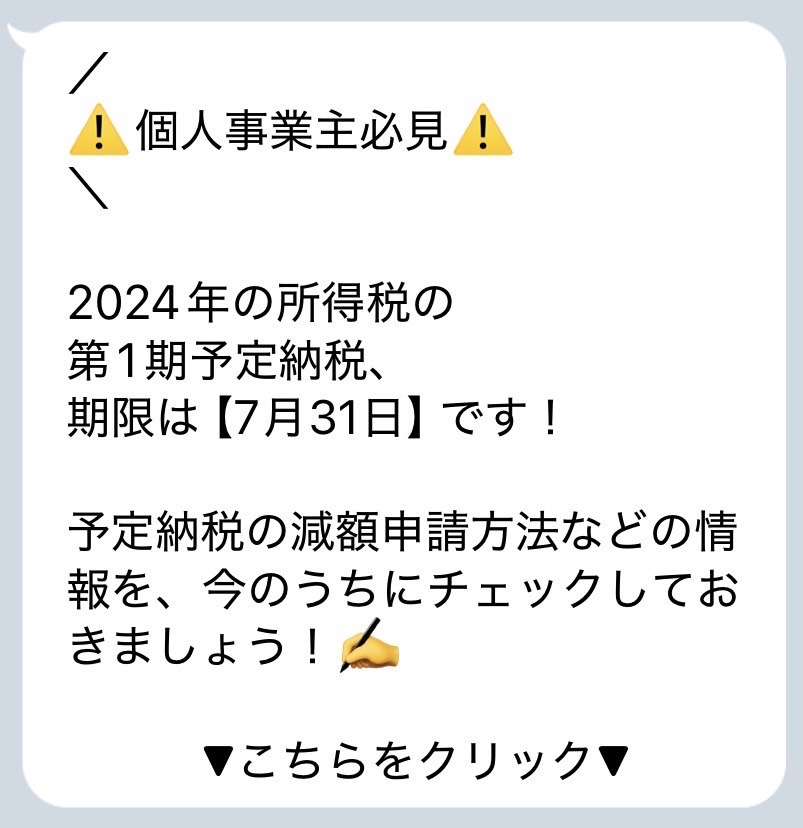
LINE登録2万超!3秒で登録はこちら↓↓
LINE限定情報配信中!
【実際のLINEトーク画面】

LINE登録2万超!3秒で登録↓↓
事業承継にあたって使える「事業承継・引継ぎ補助金」
事業承継の際につかえる「事業承継・引継ぎ補助金」は、個人事業の承継でも利用可能です。ニーズに応じて、以下3つの枠から選択できます。
- 経営革新枠:事業承継やM&Aで引き継いだ経営資源を活用して経営革新等をしたい
- 専門家活用枠:経営資源引継ぎニーズがある場合に、引き継ぎに際して活用したい
- 廃業・再チャレンジ枠:M&Aによって事業譲渡ができず、需要創造や雇用創出に資するチャレンジをしたい
対象経費は申請枠によって異なりますが、取り組みにかかる費用は補助してもらえると考えてよいでしょう。具体的には、設備費・外注費・委託費・旅費・廃業費などが対象経費となっています。
これから事業承継をしたいと考えている個人事業主は、ぜひ活用してみましょう。
申請〜補助金受給の流れ
事業承継・引継ぎ補助金の申請から補助金交付までの流れは、以下のとおりです。
申請〜補助金受給の流れ
- 認定支援期間や専門家への相談
- 交付申請
- 審査・交付決定
- 補助事業の実施・状況報告
- 実績報告
- 確定検査・補助金額の確定
- 補助金交付請求
- 補助金交付
- 事業化状況報告等
引用:事業承継・引継ぎ補助金事務局『事業承継・引継ぎ補助金 9次公募のご案内』
上記のように、交付後も報告書の提出などが必要となっています。また、審査には締切から1か月前後はかかるので、余裕をもって資金繰り計画を立てましょう。
個人事業を承継する際の注意点
個人事業を承継する場合、以下のポイントに注意しましょう。
- 親から子への名義変更でも課税対象になるケースあり
- 青色事業でないと事業承継税制は使えない
- 基本的には承継者も個人事業主になる
それでは、各注意点を詳しく解説します。
親子間の名義変更でも贈与税の課税対象になるケースあり
承継方法によって、どのような課税になるかが異なる点には注意が必要です。例えば、店舗物件を後継者に売却した場合は所得税(売り手)と消費税(買い手)の課税対象になりますが、名義変更の場合は贈与税の課税対象になります。
なお、贈与であっても不動産取得税はかかりますが、一定の要件を満たせば軽減措置を受けることが可能です。
青色事業でないと事業承継税制は使えない
前述のとおり、事業承継税制は青色事業が対象となっています。白色申告していた方は利用できませんので、ほかの税額軽減措置が利用できないか検討しましょう。
基本的には承継者も個人事業主になる
個人事業を法人化するケースを除いて、個人事業を承継した場合は、後継者も個人事業主として開業する必要があります。開業届の提出や、その他必要な手続き(青色申告、許認可等)を忘れないようにしましょう。
個人事業の承継に関するよくある質問
個人事業の事業承継については、以下のような疑問を抱く方が多くいます。
- 親子でない他人でも事業承継は可能?
- 夫婦で事業承継は可能?
- 事業承継すると借入金も引き継ぐことになる?
- 事業承継で苦労するポイントは?
それでは、よくある4つの質問について以下で回答します。
親子でない他人でも事業承継は可能?
親子でなくても、個人事業の承継は可能です。売却はもちろん、贈与や相続についても、事前に正規の手続きを踏んでいれば可能となっています。
夫婦で事業承継は可能?
夫婦間でも、事業承継は可能です。贈与・相続ももちろんできます。夫婦間の場合は、贈与・相続にするのか、売却にするかを柔軟に選択できるでしょう。
事業承継すると借入金も引き継ぐことになる?
事業承継した場合、借入金は引き継いでも引き継がなくても問題ありません。しかし、借入金込みで資金繰りをしているケースがほとんどなので、多くの場合は引き継ぐことになるでしょう。
また、相続の場合、負債も一緒に相続されます。負債相続を拒否したい場合は、すべての相続を拒否するか、相続財産の範囲内で負債を背負う限定承認の手続きをしなければなりません。
事業承継で苦労するポイントは?
中小企業庁が作成している中小企業白書によると、事業主の多くは、以下のようなポイントで事業承継で苦労しているようです。
- 後継者に経営状況を詳細に伝えること
- 後継者と引継ぎの条件を調整すること
- 取引先との関係維持
- 後継者を補佐する人材の確保
引用:中小企業庁『中小企業白書2019 第2部』
一方で『特になし』という回答は41.3%に上っており、後継者さえ見つかれば、比較的スムーズに承継できるケースも多いようです。
まとめ
個人事業であっても、法人と同じように事業承継は可能です。これまで築き上げた大切な事業を維持し、顧客にこれからも製品・サービスを提供するために、しっかりと手続きをしていきましょう。
事業承継においては、贈与・相続・売却どの方法をとるか、補助金や減税・納付猶予・免税措置を活用するかなどによって、手続きの流れが大きく変わってきます。昨今は後継者不足での廃業も増えているので、早い段階から承継について考えておくとよいでしょう。

- 個人事業の事業承継は可能だよ!
- 承継方法は贈与・相続・売却があるよ
- 補助金や税負担軽減制度の活用も検討しよう!

.png)
-485x306.png)
-485x306.png)

-485x306.png)

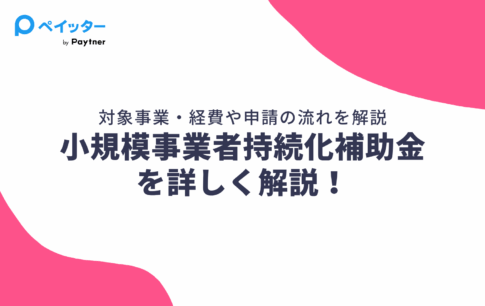

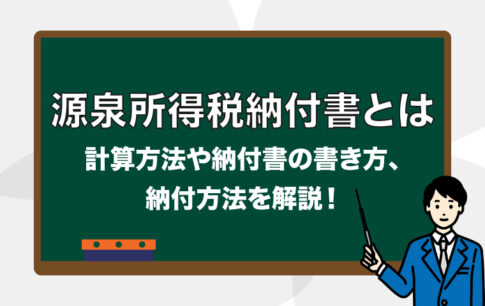
-485x306.png)
-485x306.png)
-485x306.png)

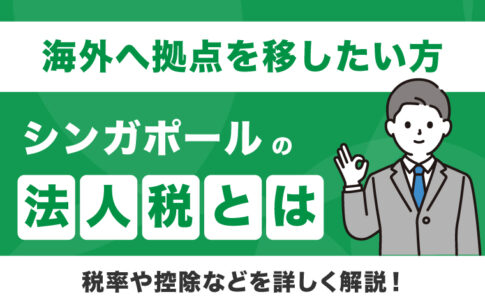
-485x306.png)

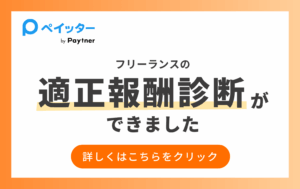
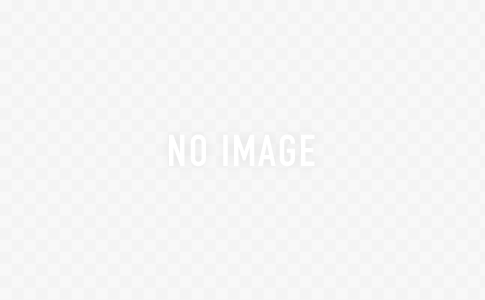
-485x306.png)
-485x306.png)
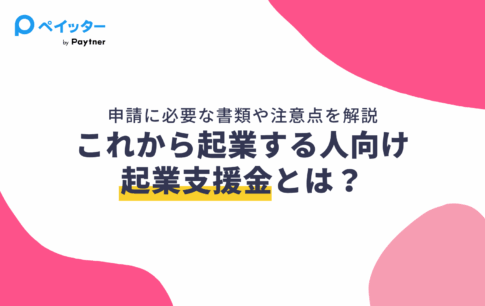
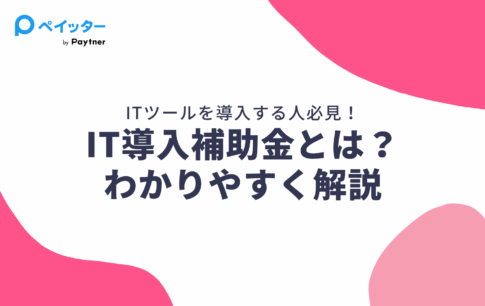
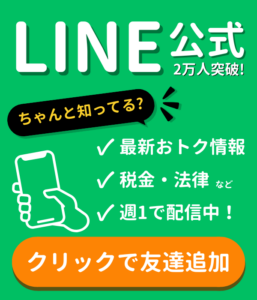
\ お金の不安、LINEで減らそう! /
フリーランスのための
「知って得する情報」を毎週配信中!
✅ 節税&経費のコツ
✅ 補助金・助成金の申請ガイド
✅ 最新の法律情報
\ LINE登録2.5万人突破! /