昨今は、会社から独立して個人事業主になる方が増えてきました。柔軟な働き方や、頑張りに応じた収入アップなどに魅力を感じて独立する方が多いようです。
本記事では、独立して個人事業主になる流れを6つのステップで解説します。開業するメリット・デメリットや、扶養についてなども解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 個人事業主として独立すれば、自分にあった働き方が実現できるかも!
- 現職と同様の事業スタートするときは、競合避止義務について必ずチェックしよう
- 確定申告や老後資金について不安がある人も、しっかりと対策すれば大丈夫!
目次
個人事業主とは?
個人事業主とは、開業届を提出して、個人で事業を営む人のことです。昨今では、デザイナー・ライター・ITエンジニア・保険営業など、さまざまな業種で個人事業主として働く人がいます。
会社員とは異なり、企業と雇用契約を結んで仕事をしません。自分自身で一般消費者に商品・サービスを売ったり、業務委託というかたちで企業から仕事をもらったりして、生計を立てています。
なお、個人事業主でも複数で事業を営んでいるケースは少なくありません。従業員を雇っていたり、家族を従業員としていたとしても、法人格でないなら個人事業主になります。
個人事業主とフリーランスの違いは?
個人事業主と似た言葉に、フリーランスがあります。個人事業主とフリーランスの主な違いは、開業届を提出しているかどうかです。
税法上、個人事業主は開業届を提出し、確定申告をして所得税を納めている人物を指します。一方、フリーランスは副業ワーカーやフリーターなど、さまざまな働き方をしている人を含む呼び方です。
会社員と個人事業主の違いは?
会社員と個人事業主では、払う税金や社会保険など、さまざまな部分が違います。主な違いとしては、以下4点があげられるでしょう。
- 働き方
- 税金
- 健康保険
- 年金
それでは、上記4つのポイントについて、具体的な違いを解説します。
働き方
会社員と個人事業主では、働き方が違います。会社員の場合、多くの方は毎日同じ時間に、同じ場所で仕事をするでしょう。個人事業主の場合は、仕事内容にもよりますが、時間や場所を選ばず仕事ができる方も少なくありません。
ただし、カフェや美容院といった店舗型のサービス業や、製造業、客先への訪問が必要な営業などは、時間や場所を選ばず仕事をするのは難しいでしょう。
税金
| 会社員 | 個人事業主 | |
| 所得税 | 〇年末調整で金額が決定 | 〇確定申告で金額が決定 |
| 消費税 | × | △※インボイス加入者のみ |
| 個人事業税 | × | △※課税売上高1,000万円超で法定業種に該当する方 |
会社員と個人事業主でおおきく異なるのが、税金です。
会社員と個人事業主どちらも払う税金としては「所得税」と「住民税」があります。そして、個人事業主の場合は、必要に応じて「個人事業税」や「(売上に対する)消費税」も納税しないといけません。
個人事業主のほうが、支払う税金の種類は多くなっています。しかし、個人事業主はより柔軟に節税ができるのが強みです。
健康保険
| 会社員 | 個人事業主 | |
| 種類 | 組合や協会けんぽの健康保険 | 自治体が運営する国民健康保険 |
| 保険料 | 給与額に応じて変動会社と折半 | 所得金額によって変動全額自己負担 |
| 扶養者 | 扶養者人数に関わらず保険料は一定 | 扶養人数によって保険料が変動 |
会社員と個人事業主では、健康保険の種類と払う金額にも違いがあります。
会社員の場合、基本的には健康保険組合・協会けんぽ・共済組合いずれかの健康保険に加入します。保険料は会社と折半です。扶養人数によって保険料が変動することはありません。
一方、個人事業主は市区町村の国民健康保険に加入します。保険料は全額自己負担です。扶養人数が増えると、保険料も増額となります。
福利厚生もないので、保険関係では個人事業主のほうが弱いと言えるでしょう。
年金
| 会社員 | 個人事業主 | |
| 種類 | 厚生年金 | 国民年金 |
| 年金保険料 | 収入により変動会社と折半 | 年度ごと一定額を払う約1.6万円ほど |
| 受給開始年齢 | 原則65歳以上 | 原則65歳以上 |
| 受給金額 | 納付金により異なる通常は国民年金より | 年度ごと定額2024年度は満額で79.5万円 |
| 遺族年金 | 遺族厚生年金遺族基礎年金子どもの有無に関わらず、妻は生涯受け取れる | 遺族基礎年金子どものいない妻は対象外 |
会社員と個人事業主は、年金の払う金額およびもらう金額も大きく異なります。
会社員は、厚生年金に加入します。年金保険料は収入によって変動しますが、会社と折半なので自己負担が少ない点が魅力です。
個人事業主は、年金制度の1階部分に該当する国民年金のみに加入します。年間の納付額は定額で、2024年度は16,520円です。会社員よりも納付額は低額ですが、そのぶん受け取れる金額も少なくなります。
また、遺族年金に関しては、子どものいない妻は対象外となるのも国民年金のデメリットです。18歳になった年度の3月31日までにある方、もしくは20歳未満の障害等級1〜2級の子どもがいない場合、妻は遺族年金を受け取れません。
独立して個人事業主になった場合の事業形態・方式
独立して個人事業主になった場合の事業形態・方式としては、以下3種類があります。
- 独自ビジネス
- 業務委託
- フランチャイズ
- 独立採算制
それでは、それぞれどんな特徴があるのかを見ていきましょう。
独自ビジネス
個人事業主のなかでも多いのは、一般消費者に対してダイレクトにサービスや商品を提供する独自ビジネスタイプでしょう。具体的には、以下のような業種が独自ビジネスタイプに該当します。
- 美容院
- ネイルサロン
- 芸能人、インフルエンサー
- 音楽家
- 美術家
- 作家
- カフェ
- レストラン
特徴は、一般消費者と密に関われる点です。一般消費者と事業者のあいだに企業が入らないので、顧客の生の声を拾いやすくなります。また、売上をフルで受け取れるのも独自ビジネスを展開するメリットです。
一方で、自分自身で仕事や売上を生み出す必要があるので、安定しにくい点には注意しましょう。業務委託のように企業が仕事を生み出してくれる働き方ではないので、どのように競合と差別化するか、コアファンをどうやって獲得するかがカギになります。
業務委託
業務委託とは、企業が「業務」の一部を外部に「委託」するものです。個人事業主は、業務委託で働くケースも非常に多くあります。
- WEBサイト開発の工程の一部を業務委託で担当
- ニュースサイトの記事を外部委託で制作
- 企業の広告ポスターを業務委託でデザイン
業務委託契約をする際は「業務委託契約書」や「秘密保持契約書(NDA)」などの書類を作成してもらい、条件等を確認したうえで契約するのが一般的です。
フリーランス保護新法が施行された後は、契約書の作成・交付が必須となりますので、契約時には必ず書類をもらいましょう。
フランチャイズ
フランチャイズ(FC)とは、お金を払って商標・商品・販売権・業務マニュアル・経営サポートなどを利用できるようになる契約です。主に、以下のような業種で積極的に取り入れられています。
- コンビニ
- 飲食店
- 学習塾
- 美容サロン
加盟店は本部とフランチャイズ契約を結び、加盟金およびロイヤリティを支払ってビジネスを行います。なお、加盟店は「フランチャイジー」、本部は「フランチャイザー」と呼ぶこともあります。
フランチャイズは、自分自身に経営ノウハウや知名度がなくてもスタートしやすいのが魅力です。お金を払えば、有名店の看板やノウハウを享受できるので、ゼロからでもビジネスを軌道に乗せやすくなっています。
一方で、加盟金やロイヤリティが高額すぎたり、フランチャイズ契約したサービスの人気がなくなって、赤字になってしまうケースも少なくありません。売上に関わらず契約金は納めないといけないので、経営が逼迫してしまうのです。
LINEであなたに合った補助金を診断!
【今すぐ】あなたの事業種別・業歴・業種に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/

LINEで補助金診断!
【今すぐ】あなたの事業に合った補助金が分かる!
\5秒で自分に合う補助金を知る!/
独立採算制
独立採算制とは、企業内の部門に対してそれぞれ経営権を付与して、各部門が独立した存在として採算を取る経営方式です。
個人事業主の場合、複数の個人事業主が集まって共同経営をするのが独立採算制に該当します。また、フランチャイズも内容によっては独立採算制に該当するでしょう。
独立採算制のメリットは、部門間での競争意識が芽生えやすく、モチベーション向上に役立つ点です。また、経営権の一部を各部門に付与するので、事業展開のスピード感や柔軟性も改善できます。
一方で、重複業務が生まれやすくなったり、部門毎の関係が悪くなりやすかったりする点には注意しましょう。スムーズな経営のため、部門間のコミュニケーション環境や、管理・評価体制の改善が重要になります。
会社から独立して個人事業主になるための6ステップ!
会社から独立して個人事業主になりたいなら、以下6ステップで開業準備を進めましょう。
- 競合避止義務をチェック
- 独立後の事業計画を立てる
- 資金繰りの計画を立てる
- 開業届を作成・提出する
- 必要に応じてインボイス等の手続きをする
- 社会保険の切り替えをする
開業までの流れを詳しく解説しますので、これから独立開業を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
①競合避止義務をチェック
まず重要なのが、競合避止義務に関してのチェックです。競合避止義務とは、現職で行っている業務と同様の仕事を、退職後に行うのを禁止する契約です。
競合避止義務が有効かどうかは、退職後の事業内容および現職の業務内容によって異なります。裁判でも、有効となるケースもあれば、無効とされる判例も多くあるのです。
今の企業に就職する際に「競合避止義務」に関する書類にサインをした方は、現在と同じような仕事で独立開業するのが難しいかもしれません。
まずは、教護避止義務に関する書類にサインしたか、サインしたなら内容はどうか、そして退職後の事業に問題がないかをよく確認しましょう。不安があれば、弁護士に確認してもらうのがオススメです。
②独立後の事業計画を立てる
競合避止義務について問題ないことが確認できたら、まずは事業計画を立てます。
事業計画とは、事業の進め方を具体的にまとめた資料です。どんな事業を・どんなスケジュールで進め・どういう結果になるか、を記載します。
決まった書式はないので、自分の使いやすい形式で作成して問題ありません。ただし、補助金・助成金の申請に際して作成するときは、項目等に関する指定がないかよく確認してください。
個人事業主は事業計画を立てなくても問題ありませんが、目標を持ってモチベーションを維持しながら仕事をするために、事業計画は大いに役立ちます。
③資金繰りの計画を立てる
事業計画とあわせて、資金繰りに関する計画も立てておきましょう。具体的には「過去」「現在」「未来」に分けて、資金の状況をまとめていきます。
- ここまでの資産(現預金・負債)をまとめる
- 現状の収入をまとめる
- 現状の生活関連の支出(固定費・変動費)をまとめる
- 事業にかかる支出(仕入費、人件費等)をまとめる
- 理想的な利益の増減を考える(月ごと)
- 理想の利益を上げるための売上の増減を計算する
個人事業主は収入が不安定になりやすい働き方です。だからこそ、資金繰りの計画を立てて、赤字・自己破産にならないようリスク管理をしておくのが重要になります。
④開業届を作成・提出する
事業に関する計画ができたら、いよいよ開業届を作成します。開業届は国税庁HPでダウンロードできるほか、税務署で用紙を受け取るのも可能です。
提出期限は、開業の事実があってから1か月以内とされています。なお、該当日が土日祝日だった場合は、その翌日が提出期限です。提出しなくても罰則はありませんが、後述するインボイスや青色確定申告などの手続きに影響が出るので、提出しておきましょう。
提出方法は、以下の4種類から選べます。
| メリット | デメリット | |
| 所轄税務署の窓口に持参 | 記入内容に関する相談可能 | 混雑時は時間がかかる開庁時間しか提出できない |
| 所轄税務署の時間外収受箱に投函 | 時間に関わらず提出可能 | 税務署に行く必要がある |
| 所轄税務署に郵送 | いつでも提出可能 | 郵送費用がかかる用紙を印刷する必要がある |
| e-Taxで提出 | いつでも提出可能印刷する必要がない | 記入内容に関する相談不可e-Taxの利用手続きが必要 |
記入内容に不安のある方なら所轄窓口に持参、忙しく時間のない方は時間外収容箱投函・郵送・e-Tax提出のいずれかで対応しましょう。
なお開業届の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
⑤必要に応じてインボイス等の手続きをする
開業届を提出する際には、必要に応じて以下の手続きも行ってください。
- 青色申告承認申請書
- 適格請求書発行事業者の登録申請書
- 消費税簡易課税制度選択届出手続書
「青色申告承認申請書」は、確定申告を青色申告で行いたい方が提出する書類です。青色申告だと、最大65万円の控除を使えるので、大きな節税効果があります。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」は、いわゆるインボイス制度に関する書類です。提出すると、登録番号が付与され、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者になります。
「消費税簡易課税制度選択届出手続書」は、消費税の計算方式に関する書類です。インボイス発行事業者になると、消費税の納税が求められます。この消費税の計算に関して、より簡単な計算方式で納税額を算出したい方については、以下の手続きが必要になります。併せてご覧ください。
⑥社会保険の切り替えをする
個人事業主になったら、健康保険と年金の切り替えが必要です。どちらも住んでいる自治体の役所にて行えます。
保険の切り替え期限は、退職日翌日から14日以内です。ただし、会社員時代の保険を任意継続する場合は、退職日翌日から20日以内が切り替え期限となります。
切り替え手続きをしていないと、保険の空白期間ができてしまいますので、注意しましょう。
※退職時に注意すること
退職時に注意していただきたいのが、人間関係です。
個人事業主になると、誰が顧客になるか分かりません。もしかしたら、退職する会社の人が顧客になったり、重要顧客と関係が深かったりするかもしれないのです。
退職前に仕事や人間関係をおざなりにした結果、個人事業において大きな悪影響を及ぼす可能性は十分にあります。辞めるからといって適当にせず、仕事は精一杯行い、人間関係もできる限り良好になるよう努力したうえで退職しましょう。
独立して個人事業主になるメリット
会社から独立して個人事業主になると、以下のようなメリットがあります。
- 勤務時間や場所の制限がほぼない
- 頑張り次第で収入が増える
- 節税対策を柔軟に行える
- 何歳まででも働ける
それでは、具体的にどういったメリットがあるのか、以下で見ていきましょう。
勤務時間や場所の制限がほぼない
個人事業主について「時間や場所に縛られない自由な働き方」という点を魅力に感じる方は多いでしょう。
実際、個人事業主のなかには、PC一台あればどこでも働けるという方が多くいます。デザイナー・ライターなどは、その代表例です。
勤務時間や場所の制限がないので、プライベートの時間を確保しやすいのが大きな魅力でしょう。また、家事や介護が忙しくても、柔軟な働き方が実現できます。
頑張り次第で収入が増える
頑張り次第で収入を増やしやすいのも、個人事業主の魅力です。
会社員の場合は固定給なので、頑張りに応じて月ごとの収入が大きく増えることはありません。歩合制であれば結果が収入に繋がりやすいですが、フルコミッションでもない限り、頑張りが反映されにくいと感じるのではないでしょうか。
一方、個人事業主は売上がそのまま収入になるので、自分の頑張りを実感しやすい働き方です。自分の理想金額に向けて、モチベーション高く頑張れる方には非常に適した働き方と言えるでしょう。
節税対策を柔軟に行える
個人事業主は、さまざまな所得控除をつかって節税できます。それでは、2024年度現在で使える控除を見てみましょう。
- 基礎控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 雑損控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 寄付金控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
上記のように、さまざまな控除を利用できるので、会社員時代よりも納税額を減らせる可能性もあります。
あわせて、ふるさと納税やNISAなどの制度をうまく活用すれば、より効果的な節税対策ができるでしょう。
何歳まででも働ける
定年制を導入している企業だと、60〜65際で定年を迎えます。会社員だと、65歳を超えて働くのは難しいケースが多いのです。
しかし、個人事業主に定年はないので、働こうと思えば70歳でも80歳でも働けます。自分の好きな仕事を一生涯続けられるのは、個人事業主として働くうえでの大きなメリットです。
独立して個人事業主になるデメリット
独立開業にはさまざまなメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
- 確定申告が面倒
- 即開業した場合は失業手当の対象外になる
- 収入が安定しない
- 退職金や年金などが手薄
デメリットまで細かく把握したうえで、本当に独立すべきかを慎重に考えましょう。
確定申告が面倒
個人事業主の多くが「確定申告が面倒」と言います。実際、収支や経費などについて、1つ1つ記録していく作業は非常に面倒です。人によっては、締切直前は確定申告が大変で仕事が手に付かないほどと言います。
しかし、確定申告の作業は、日頃から少しずつやっておけば大きな負担になりません。例えば、週末にその週のレシートをまとめておいたり、月末に売上を記録しておいたりすれば、締切直前になって慌てることはないのです。
また、昨今では確定申告ソフトが発達し、非常に使いやすくなっています。ソフトによっては、クレジットカードや銀行口座と連携して、自動でデータを作成してくれる種類もあるほどです。
確定申告業務の進め方や、ツール選びを工夫すれば、それほど大きな負担にはならないでしょう。
即開業した場合は失業手当の対象外になる
会社を退職して再就職しなかった場合、通常は「失業手当」がもらえます。しかし、退職してすぐに開業してしまうと、この失業手当はもらえません。
そもそも失業手当(失業保険)とは、再就職を支援するための資金支援制度です。無職の方が対象となっているため、即開業した方は対象外になってしまいます。
しかし、開業するタイミングを少し遅らせられれば、失業手当をもらったうえで独立開業することが可能です。詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
収入が安定しない
個人事業主になると、固定給がなくなり収入が不安定になります。会社員時代の何倍も稼ぐ人がいる一方で、たった1年で約3割が廃業してしまうほど、売上を立てるのが難しい働き方でもあるのです。
廃業を防ぐための対策をしておけば、少なくとも3年ほどは耐えられるでしょう。具体的な対策としては、1年分の生活費を貯めておく、人脈を広げる、SNSを活用して認知度アップを図るなどがあげられます。
また、どうしても売上が立たないのであれば、一時的にアルバイトをするのもOKです。会社員と違い固定給がないものの、さまざまな方法を使って柔軟に生計を立てられるのも、個人事業主の強みです。
退職金や年金などが手薄
会社員と比べて、個人事業主は退職金や年金といった老後の資産問題が深刻化しがちです。
そもそも個人事業主には、退職金制度がありません。年金は、会社員と異なり1階部分しか保険料を納めないので、年金受給額も少なくなります。
しかし、NISAやiDeCoを活用して老後資金を積み立てたり、小規模企業共済や付加年金制度を使って受け取れる年金を増やしたりして、対策は可能です。
また、iDeCoや小規模企業共済は、節税にも効果的です。税金対策をしつつ、老後資金を柔軟に積み立てられる点では、会社員よりも優れていると言えるでしょう。
\事業の悩み、LINEで解決/
フリーランスのための
「事業を伸ばす」情報を毎週配信中📝
✅ 節税&経費のコツ
✅ 資金繰りのポイント
など、LINEで事業成長⤴️⤴️
\5秒でLINE登録!/

\ LINE登録2.5万人突破!/
\事業の悩み、LINEで解決/
「事業を伸ばす」
情報を毎週配信中📝
✅節税&経費のコツ
✅資金繰りのコツ
など、LINEで事業成長⤴️⤴️
\ LINE登録2.5万人突破!/
個人事業主が独立前に使える助成金・補助金・融資
これから独立する方は、開業資金を調達するのに苦労する方が多いでしょう。以下のような資金調達方法を活用すれば、余裕をもって事業をスタートできるはずです。
- 各自治体の創業助成金・補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- 事業承継・引き継ぎ補助金
- ものづくり補助金
- 日本政策金融公庫の創業時支援
- 創業時OKのビジネスローン
以下の項目では、各制度について詳しく解説します。
各自治体の創業助成金・補助金
各地方自治体では、創業時に申請できる助成金・補助金制度を用意しています。
例えば東京都の「創業助成金(東京都中小企業振興公社)」では、100〜400万円の創業時支援を受けることが可能です。申請条件として、創業支援プログラムを受けていることが必須となっており、個人事業開業に関する教育を受けたうえで資金支援を受ける流れとなっている点も非常に魅力的です。
自治体ごとに金額や申請内容は異なりますので「創業支援 + (住んでいる自治体)」の2ワードで検索してみましょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓や業務効率化といった取り組みにかかる経費の一部を補助してくれる制度です。
申請枠は「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「操業枠」から選択できます。補助率は基本2/3、補助金上限は通常枠が50万円、その他が200万円です。
申請に際しては「経営計画書」および「補助事業計画書」を作成するとともに、「事業支援計画書」を管轄の商工会議所に提出する必要があります。書類準備に関しては少し手間がかかりますが、創業時でも利用しやすい補助金です。
IT導入補助金
IT導入補助金は、ITツールの導入によって業務効率化やセキュリティ対策強化などをしたいと考える事業者に向けた制度です。ツールの導入費用の一部を補助してくれます。
申請枠には「通常枠」「インボイス枠(インボイス対応類型)」「インボイス枠(電子取引類型)」「セキュリティ対策推進枠」「複数社連携IT導入枠」の5つがあります。申請枠によって異なりますが、おおよそ1/2〜2/3、上限100〜300万円程度の補助を受けることが可能です。
なお、セキュリティ対策ソフトやクラウドサービスといった「ソフトウェア」だけでなく、タブレットやレジなどの「ハードウェア」も補助対象となっています。
ITツールを多く購入する場合には、ぜひ活用してみてください。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金とは、既存ビジネスを再編・統合・経営陣刷新するなどして、事業の立て直しを検討している方に向けた制度です。事業承継や引継ぎにかかる経費を補助します。
申請枠は3種類ありますが、創業時の場合は「創業支援枠」を利用可能です。ただし利用できるのは、廃業予定の事業者から、事業譲渡や株式譲渡などを受けて、経営を引き継ぐかたちで創業する方に限ります。
すべての方が利用できる訳ではありませんが、もし条件が合うようであれば、活用してみましょう。
ものづくり補助金
ものづくり補助金は、試作品・製品・サービスの開発や、生産性向上などに取り組む事業者を支援するための資金支援制度です。製造業限定のように感じてしまいますが、以下さまざまな業種の方が利用できます。
- 製造業
- 建設業
- 運輸業
- 旅行業
- 卸売業
- サービス業
- 小売業
- ゴム製品製造業
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス業
- 旅館業
- その他の業種
補助上限額や補助率は事業規模によって異なりますが、従業員5人以下なら上限額750〜1,000万円程度、補助率1/2〜2/3程度です。
基本要件として「給与支給総額の増額」「最低賃金の引き上げ」「付加価値額の増加」の3つがあります。補助事業を通じて、事業の価値や賃金を引き上げられる見込みがあるかどうかが、大きなポイントです。
日本政策金融公庫の創業時支援
融資を検討している方であれば、日本政策金融公庫の創業時支援がおすすめです。
日本政策金融公庫とは、銀行やその他金融機関からの融資を受けにくい中小企業や創業間もない事業者などに対して、資金支援を行うための機関です。日本政府が株式を100%保有しており、財務省管轄の政府系金融機関として運営されています。
利用者にあわせて、さまざまな融資制度が用意されているのが魅力的でしょう。
- 新規開業資金(通常の支援制度)
- 新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
- 新規開業資金(再挑戦支援関連)
- 新規開業資金(中小企業経営力強化関連)
日本政策金融公庫の創業時支援は、担保や保証人などに関して柔軟に検討してもらえるのが利点です。融資上限額も7,200万円と非常に高額なので、大規模な資金調達をしたい方にぴったりです。
創業時OKのビジネスローン
ビジネスローンによっては、創業時の方でも申し込めるものがあります。
そもそもビジネスローンとは、いわゆるカードローンの事業用バージョンのようなものです。用途は原則として事業用に限られますが、カードローンと異なり、収入の1/3を超えて借入ができます。
通常は収入証明(確定申告書など)が必要ですが、創業時OKのビジネスローンであれば、個人事業に関する収入証明は必要ありません。しかし、別途さまざまな書類が必要になる可能性があるので、事前に問い合わせておいたほうが良いかもしれません。
独立して個人事業主になっても、扶養内で働ける?
独立して個人事業主になる方のなかには「収入を減らして、扶養内で働きたい」と考える方もいるでしょう。
売上金額によりますが、個人事業主として働きながら、家族の扶養に入るのは十分に可能です。以下では、そもそも扶養とはどういった制度なのか、収入がいくらなら扶養に入れるのかを詳しく解説します。
そもそも扶養とは
扶養とは、子どもや専業主婦など自分自身のみで生計を立てるのが難しい方が、家族に経済的支援を受けるための制度です。
扶養に入ると、扶養者(支援する側)の所得税や社会保険料などが減額されます。また、被扶養者(援助される側)は、保険料を払わなくても良くなります。扶養者・被扶養者ともに経済的負担が少なくなるのが、扶養の魅力です。
扶養に入るための条件
扶養に入るための条件は、税法と社会保険とで異なります。今回は、一般的に「扶養に入る」と言う際に意味する「保険」に関する扶養の条件を解説します。
社会保険上の扶養に入るための条件は、扶養者がどんな保険に加入しているかで異なりますが、一般的には以下のような条件となっています。
- 被保険者の配偶者、第三親等まで方、もしくは事実婚や同一生計の事実がある方
- 年間収入130万円未満(60歳以上や障がい者は除く)
※収入は「基本的に前年の所得及び直近3ヶ月の収入」から見込額を計算
つまり、年間の収入を130万円未満に抑えれば、個人事業主として働きつつ、扶養に入れるのです。
個人事業主として独立する際によくある質問
個人事業主として独立したいと考えている場合、以下のような疑問を抱く方が多いようです。
- 個人事業主として独立すると保育園に入れる?
- 独立採算制って何?
- 補助金と助成金ってどう違うの?
以下の項目では、よくある質問3つにそれぞれ回答していきますので、これから独立開業を目指している方はぜひ参考にしてください。
個人事業主として独立しても保育園に入れる?
個人事業主として独立しても、保育園に入ることは可能です。ただし、一般の会社員と比べて勤務時間が把握しにくいため、利用しにくくなるケースもあります。
個人事業主として独立した後に、保育園を利用するためには、以下の書類が必要になります。
- 就労証明書
- 開業届
- 業務に関する契約書
- 確定申告と所得税納税に関する書類
- 事業の実態が把握できる書類
必要書類は自治体によって異なりますが、少なくとも事業の実態が把握できる書類は必要です。事業内容に関する書類については、特に勤務実態を細かく記載し、保育園が本当に必要であることが分かるようにしましょう。
独立採算制って何?
独立採算制とは、各部門ごとに経営権限を付与して、それぞれが利益を追求していく経営方式です。各部門が独立して採算を取っていくので、独立採算制と呼ばれます。
個人事業主の場合は、複数の個人事業主が集まって、お互いに経営権限を持ちながら共同経営をしていく場合が独立採算制に該当します。
また、企業から経営権限の一部を譲渡してもらい、個人事業主として採算を取っていく場合も、独立採算制と言えるでしょう。
補助金と助成金ってどう違うの?
補助金と助成金の違いは、不採択の確立です。
補助金は利用に際して審査があり、不採択になる可能性も十分にあります。補助金には予算があり、申請件数が多いほど採択される確立は低くなってしまうのです。
一方、助成金は条件を満たす方であれば、基本的には採択されます。しかし、金額は補助金に比べて少ない傾向にあり、対象経費の範囲も狭い傾向にあるため注意が必要です。
まとめ
会社を退職して独立する方は、まず競合避止義務についてのチェックが必要です。また、退職後の事業や資金繰りについて計画を立てるのも、事業をうまく軌道に乗せるためには重要になるでしょう。
収入・確定申告・社会保険など、さまざまな疑問や不安があると思いますが、本記事で紹介した流れに沿って手続きをすれば問題ありません。ただし、税金や保険についてはそれぞれのケースに合わせた対応も必要なので、本サイトの関連記事なども参考にしながら、情報収集に努めてください。

- 個人事業主として独立すれば、自分にあった働き方が実現できるかも!
- 現職と同様の事業スタートするときは、競合避止義務について必ずチェックしよう
- 確定申告や老後資金について不安がある人も、しっかりと対策すれば大丈夫!

.png)
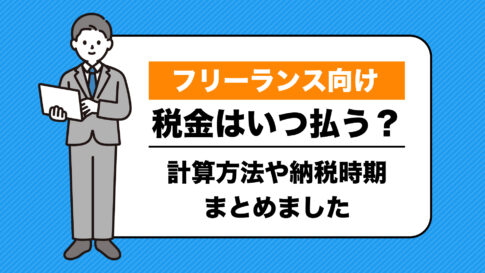
-485x306.png)
-485x306.png)
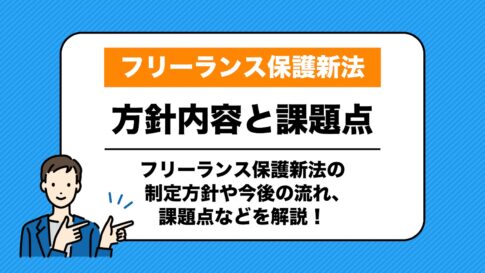
-485x306.png)
-485x306.png)
-485x306.png)
-485x306.png)
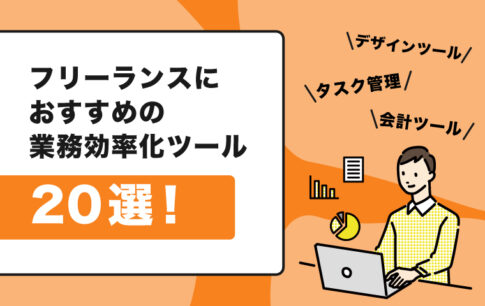
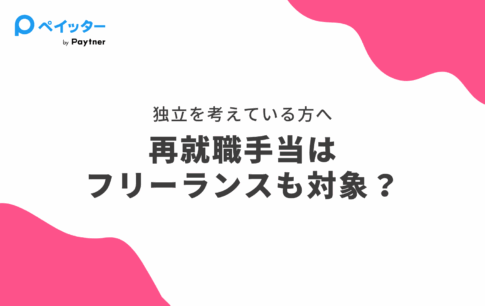
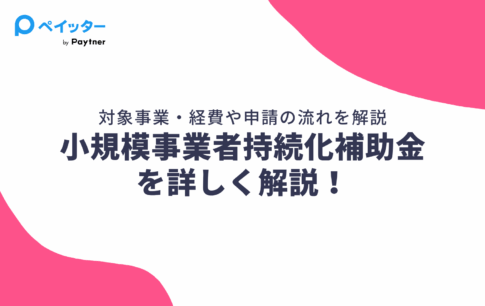
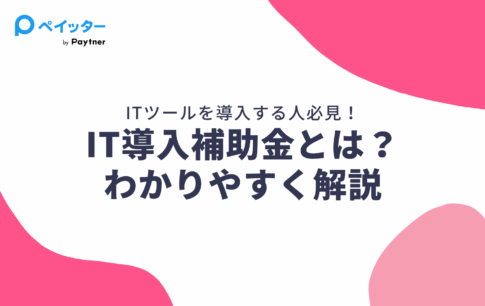
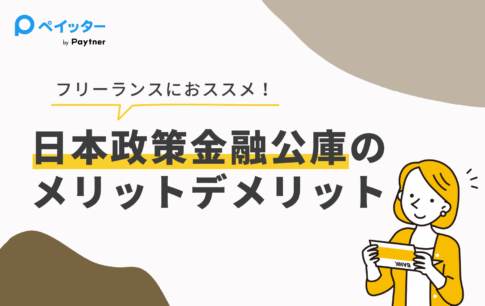
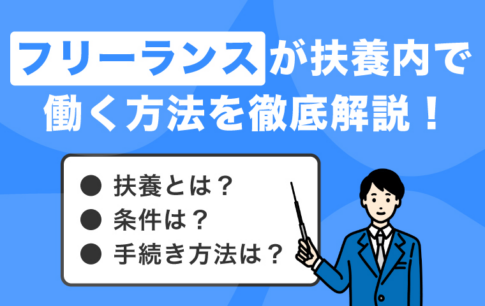
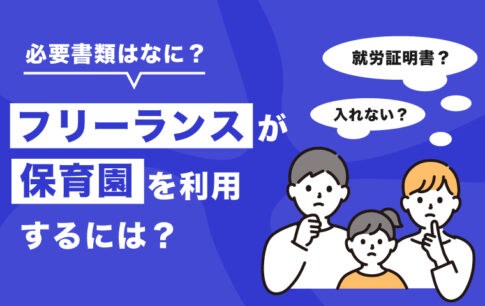

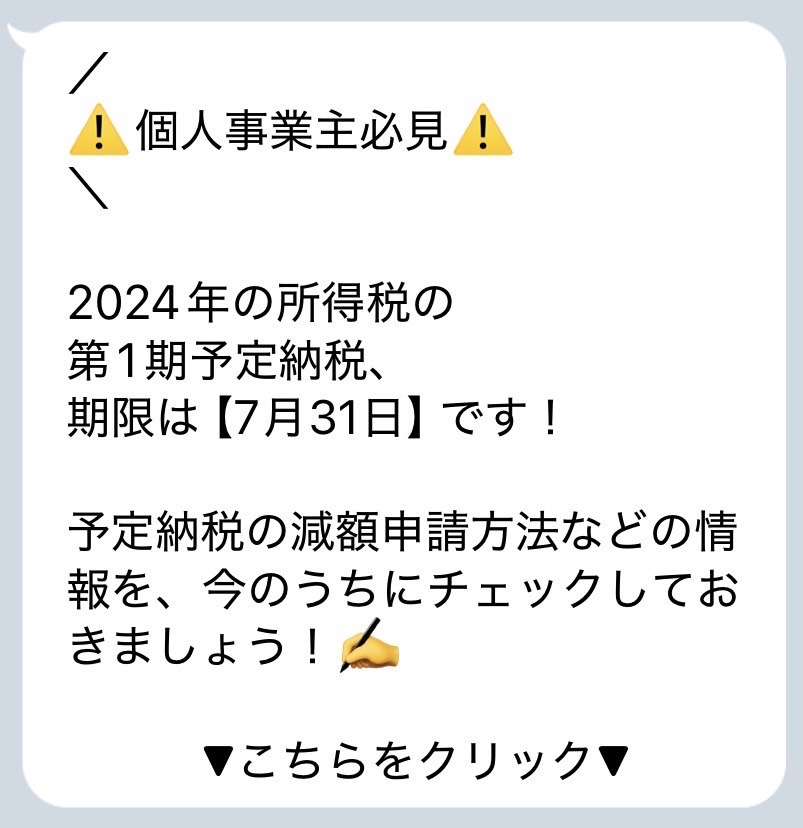
-485x306.png)
-485x306.png)

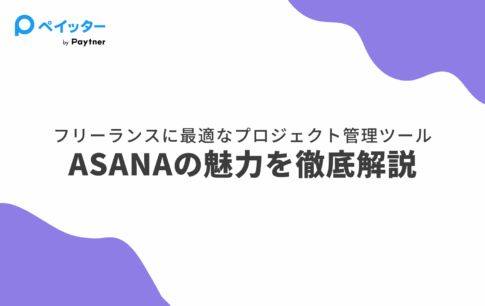
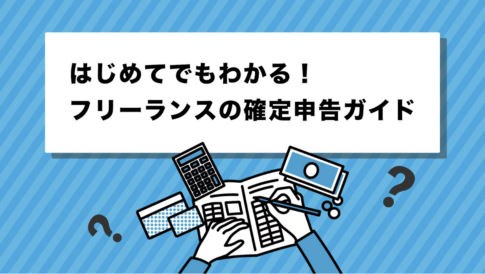
-485x306.png)
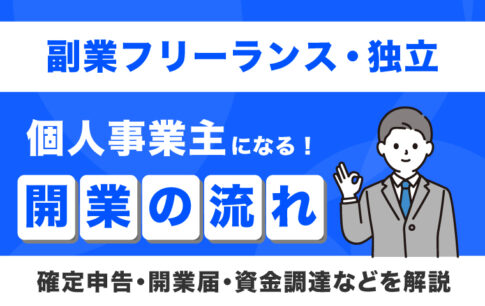
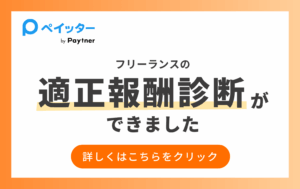
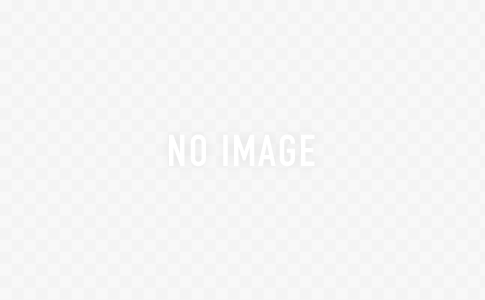
-485x306.png)
-485x306.png)
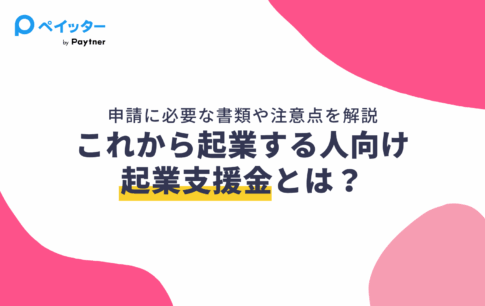

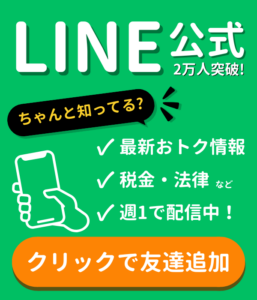
\ お金の不安、LINEで減らそう! /
フリーランスのための
「知って得する情報」を毎週配信中!
✅ 節税&経費のコツ
✅ 補助金・助成金の申請ガイド
✅ 最新の法律情報
\ LINE登録2.5万人突破! /